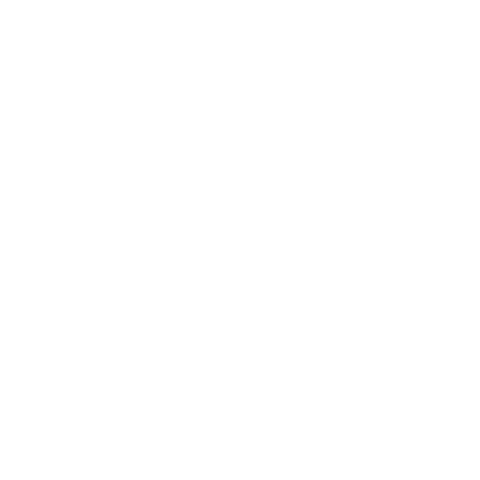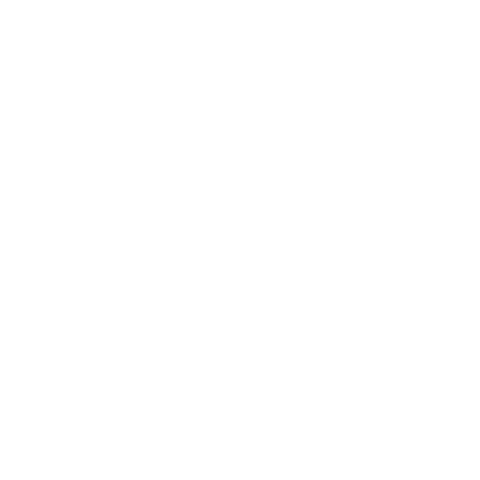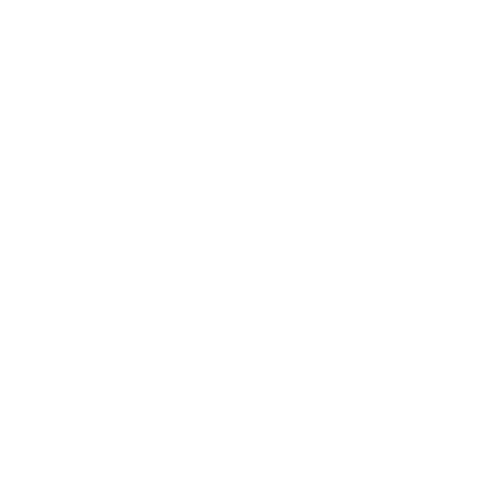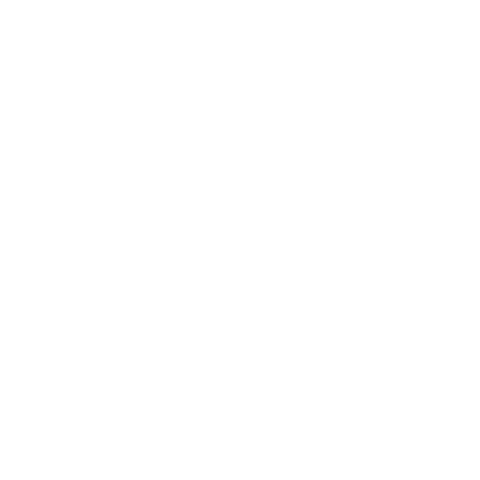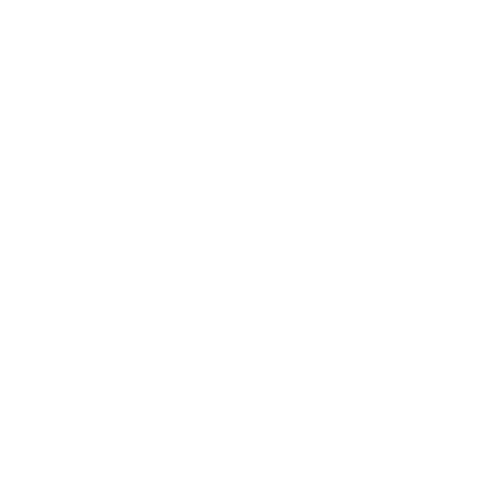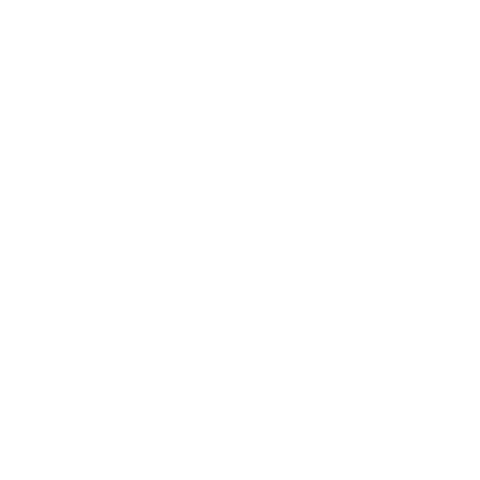御朱印は、日本で寺社でお受けする寺社の印です。
寺社の御朱印を御朱印帳に集める方も大勢いらっしゃいます。
私の亡くなった祖母もその一人、何冊も御朱印帳を大切に保管していました。亡くなったとき、御朱印帳はお棺に納められました。
御朱印には長い歴史があり、1,000年前から日本にあったとされています。
この習慣は、写経を寺に奉納し、その奉納の証拠として印と証明書を受け取ったことから始まったと考えられています。
その後、12世紀ごろから、日本の寺社を訪れる巡礼者の数が増加し、御朱印を受ける習慣が広く普及しました。
17世紀以降、寺社参拝が一般に広まり、御朱印集めの文化が日常的なものとなりました。
庶民の巡礼は、楽しみとしての旅行も兼ねており、御朱印は旅の記念でもあったのでしょう。
御朱印の料金は300円から500円程度です。
一部の寺社では、切り絵など芸術的な御朱印があり約1,000円程度が目安。
通常、御朱印帳を寺社や神社の社務所に渡して御朱印をいただきます。
しかし、コロナパンデミック以降、書置きの紙が渡されることもあります。
この紙は、御朱印帳に貼り付けるようになっています。
寺院や神社の職員の大半は、書道が上手です。
書道は日本の文化と芸術であり、御朱印を通じて手軽に見ることができます。
もちろん、これは神聖なものですから、大切に保管してくださいね。
御朱印コレクターには、信仰心の厚いご隠居だけでなく、若い女性や外国人観光客もいます。
興味がある場合は、寺社事務所に聞いてみてください。御守りを販売するコーナーが、御朱印の窓口でもあります。
かぐやライゼビューローでは、寺社を巡るガイドを手配できます。
おみくじと御朱印の両方に興味がある場合でも、お手伝いできます。おみくじは通常、日本語のみで書かれていますから説明が必要ですよね。
おみくじに興味がある場合は、私の以前のブログ記事をご参照ください。